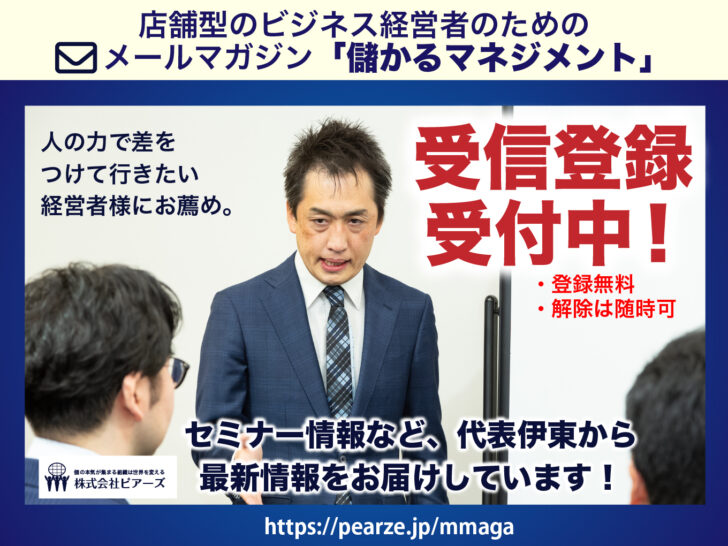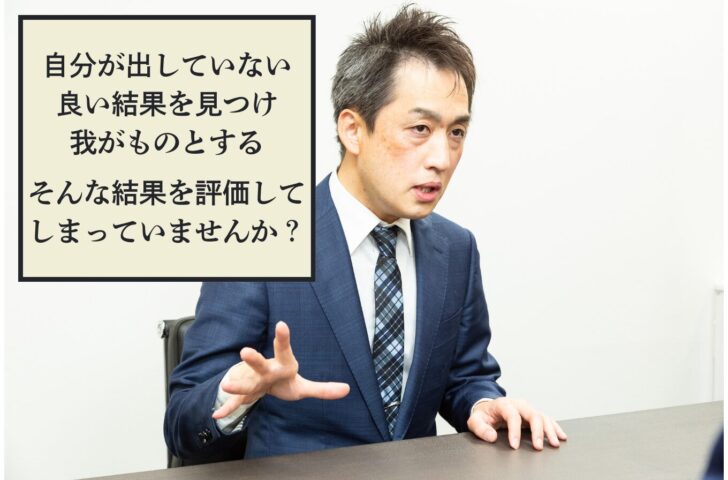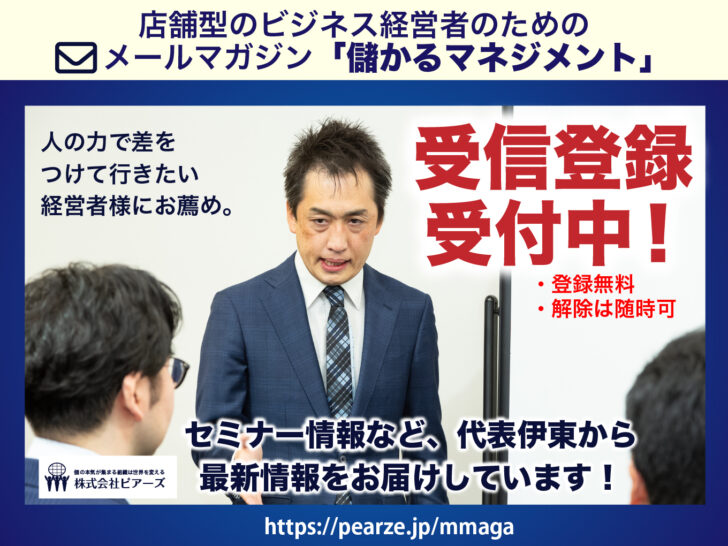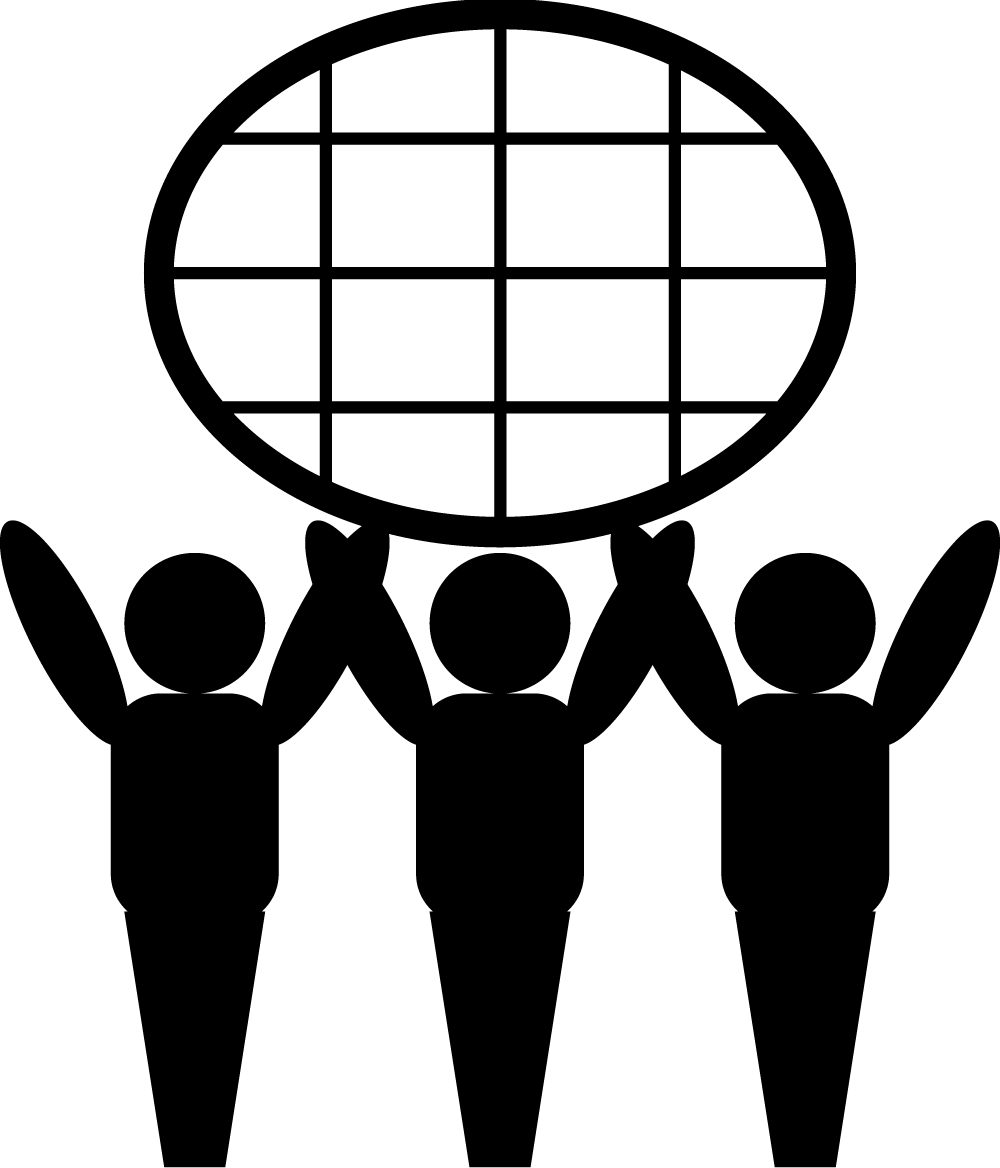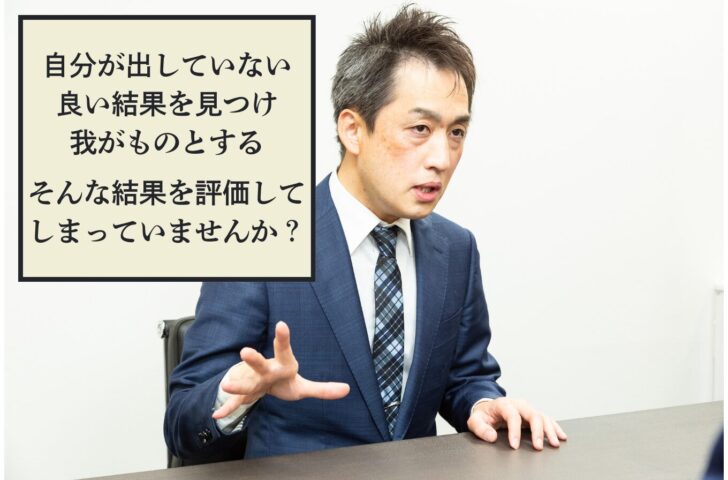
「ズルしていた社員はいなくなりました」
「ズルを容認してた社員も」
ある社長がおっしゃいました。
店舗型のビジネスにおいて、このワードを使っている社長もいらっしゃるのではないでしょうか?
「結果を出しなさい」
実はこのワードには毒が含まれています。
この毒の存在が見えていないと、いつのまにか会社に蓄積されていき、やがては成長を止める、人手不足に陥るといったおそろしい症状として現れてきます。
では、その毒とは何なのか?
それは
「どうしたら良い結果を自分の手柄にできるのか?」など、おかしな方向に力を入れる人が現れる
です。
例えば
たまたま好調だったのに「それは、私が努力した結果なんです」
または
意図してないポイントで良い結果が出たのに注目して「実は私がそうなるように手をうっていたからです」
あるいは
部下が出した成果を見て「私はこんな指示を出してましたから」
ここまでご覧になった方には
「まさか」
「そんな社員、本当にいるの?」
と思われるでしょうか。
まるでマンガに出てくる腹黒いキャラのような話ですが、現実に起きることです。
社長が欲する「汗を拭いつつ、今日もまた努力を重ねてコツコツと・・・」という姿はそこにありません。
逆に目に入ってくるのは、PCばかり見ている人達。
「何か、どこかに良い結果は無いものか」
「お、これ・・・使えるかな?」
汗など一滴もかかず、棚ボタ狙い。
日々磨き上げようとする腕は、ズルの精度。
さてここで
「もし、そんな結果だけ横取りするような社員が存在したとしても、上司の目があるでしょ」
「さすがに気付かれて怒られるんじゃないの?」
と言われるところでしょうか。
そんなチェック機構が機能していれば苦労しません。
問題なのは、その上司自身だからです。
ある大企業で働いていた元社員がこう言いました。
「今振り返ると、あれは異常でした」
「発表する内容の初手は『まず探すことだ』と教えられましたから」
・良い結果を見つけてからが腕の見せ所
・評価される、されないのラインはどのへんにあるのか。そのラインを超えよ。
・あたかも自分が努力したかのように見せつけられる方法はこうだ。
「当時の私は、それを聞いても疑問さえ抱きませんでした」
「それどころか『なるほど!』と前のめりでしたから」
なぜこういった異常が当たり前となってしまうのか?
私が推測するに、その原因はこのワードが世に定着しているからではないか?と見ています。
それは
「結果が全て」
これは本来、口ばかりで行動しない人達に対して
「そうか、実際に結果まで出さないと会社は認めてくれないのか」
と、なっていただく為に使える言葉です。
できればそういった人だけに使ってほしい言葉ではありますが、この言葉の恐ろしい所はこれさえ言ってれば間違いないと捉えられる点。
深く考えず「結果だ」「まず結果を出してから言いなさい」「能書きはいらない」「先に結果を見せなさい」
聞いてる側としては厳しい言葉です。
我慢が限界に達したからなのか、言われる側にはやがてこんな人が現れます。
「じゃあ結果さえ出せればいいんだ」
「余裕じゃないか」
「だって、そこから逆算で『やったったりました』って言えばいいんだから」
どこかに転がっていた良い結果、
決して自分が努力して出した結果ではないが、結果は結果。
「さすが◯◯君、よくやった」
「良い結果じゃないか」
「そういうのがいいんだよ」
努力もせずに、良い結果を見つけては我が物にしようという意識が定着してしまっている企業。
その後はどうなっていってしまうのでしょうか?
どうしたらこういった事態を防げるのか?
私がおすすめする方法は1つ。
「もしかしたらそういう人が現れるかもしれないぞ」
社長や組織のトップがそんな視点を持っておく、です。
別に「結果が全てと言うな」など、お触れを出す必要はありません。
視点さえあれば、異常を感知でき、すかさず指摘することができます。
それが何度か続きますと
「そうか、こういった結果は会社は必要としていないんだな」
となっていきます。
結果を出しなさいの解毒は結構早く実現できるものです。
ビジネスシーンにおいて、便利なワードはこの他にもたくさんあります。
「いま我が社に定着しているワードにおかしな毒が含まれていないか?」
社長や組織のリーダーには、そういった視点が必要なのではないでしょうか?