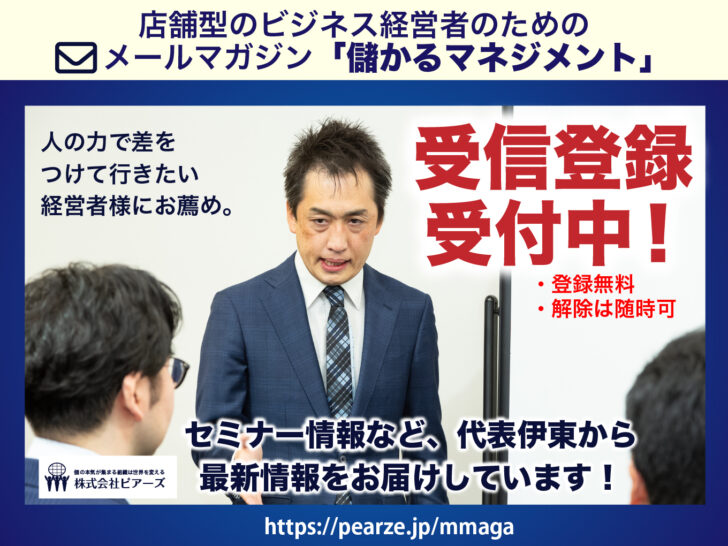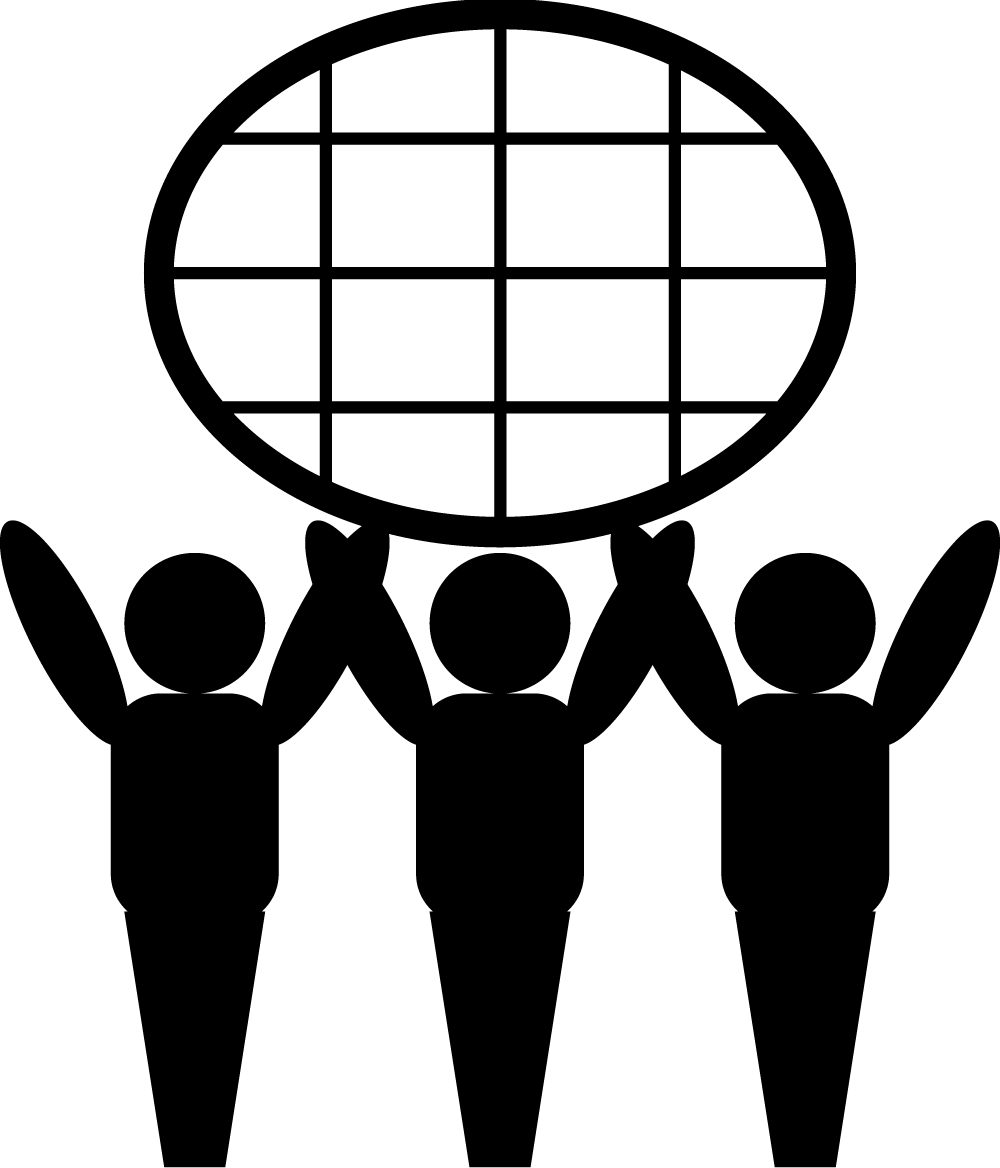今週のマネジメント 第480号 部下のせいにする上司がいなくなる法
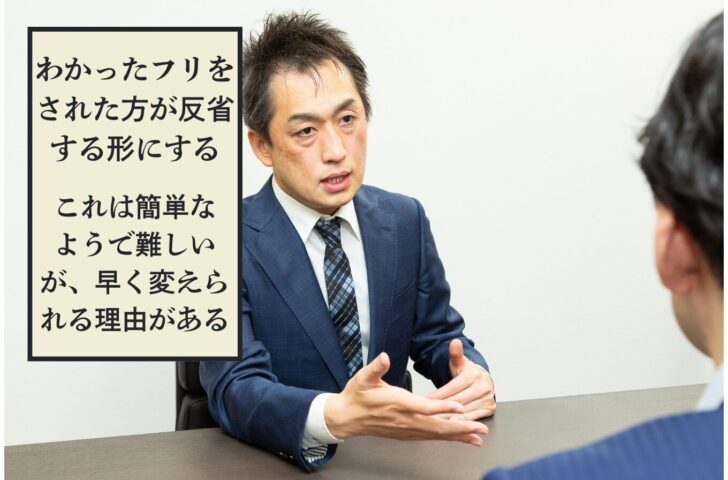
「伊東さん、平気で部下のせいにする人っていますよね?」
「口では『私の責任です』とは言ってるんですが、本当は部下が失敗したからですって感を醸し出してまして・・・」
ある社長がおっしゃいました。
上司は本来、部下を守る立場の人。
ところが残念なことに「部下のせいにする上司」が現れることがあります。
上記の社長がおっしゃった人はまだマシな方で、もっとひどい人は
「なぜ君の部署で問題が起きてしまったのか?」
と尋ねた時、平気でこう返されたりします。
「本人がハイと言ったんで・・・」
この一言を聞いただけで、
「あ〜 もういいから」
とそれ以上口にしてもらいたくないと、即シャットアウトという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
店舗や会社などの組織内には、たまにこんな声が耳に入ってきたりします。
「わかったって言ったのお前だよな?」
「ほら、◯月◯日 記録残ってるぞ!」
つい「あれ? ここって裁判所だっけ?」
再発防止をどうするか?
大事な目的はどこへやら。
またある店舗や、組織の喫煙所では
「この前、また◯◯がミスしちゃって」
「またぁ〜? アイツ大丈夫?」
「なになに何の話? また◯◯が何かしたの?」
「今度は何やらかしちゃったのよ?」
まるでお昼のワイドショー状態。
そこには我々にとって大事な仲間、という概念はありません。
こういった「管理監督者である上司が平気で部下のせいにする」という問題。
いつか解決できればそれでいい・・・というわけにはいきません。
なぜなら、その間にも犠牲者は次々に増えていき、ギブアップする人も現れてしまうからです。
会社として対策を急がないと、社長にとって貴重な人材が次々に失われていってしまいます。
いち早くこの問題を解決したい!
そう考えている社長もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、この問題の解決はなかなか複雑です。
苦労して対策を確立したのに、「あ〜、その視点が無かった」となり、また一からやり直し・・・。そんなこともありえます。
そうならないためにも本コラムにおいても、何かお手伝いできないか?
短いながらもポイントを1つご紹介致します。
それは
わかったフリをされた方が反省する形にする
例えば商売人が、気合を入れて、ある商品を用意したのに予想以上に売れなかったらどう考えるでしょうか?
「客が悪いからだ」
「買わない人達はオカシイ」
となるでしょうか?
そんな人は100%いないとはいい切れませんが、大半の方はきっとこう考えることでしょう。
「場所がいけなかったのだろうか?」
もしくは
「いや時間が悪かったのかも」
「別の曜日の方が良かったか?」
「いや、もっと商品自体を目立たせる必要があるのでは?」
「量が足りなかったに違いない」
「おそらく宣伝が足りなかったからだ」
商売において、予想よりも売れなかった時に考えることは
「売る側に問題があったのではないか?」
です。
なぜなら、そうしなければ改善点が見つけられず、いつまでも売れるようにすることができないからです。
つまり、こういったビジネスマンの基本である考え方を、店舗型のビジネスのマネジメント面にも根付くようにすればいい、ということです。
ただ、ここで気をつけなければならないのは、モノやサービスが売れなかった場合、売上が立たないわけですから、「ああ売れなかったな」とすぐわかることですが、会社や店舗などの組織のマネジメントにおいて、伝えたいことがうまく伝わったかどうか?
それはすぐわかることではありません。
上司の言ったことに
「よくわかりませんでした」
などとストレートに言われることはまず無いからです。
ただ、
わからなかった人はどんな反応をするのか?
これは、人を指導する立場にある人であればすぐわかることでしょう。
さてここで
「なんだそれだけ?」
と言われる所かもしれませんが、実は簡単ではありません。
やってみるとわかりますが、これがなかなかうまくいかないものです。
まるで「この人はきっとこう考えているのではないか?」と思うほどです。
「こんな無能を雇った会社が悪い」
「私は悪くない」
なぜ指導する側の上司が反省してくれないのか?
それはおそらく、多くの企業に昔からこの「部下が悪いから」といった、悪しき風習が定着していたからだと見ています。
今と違って、昔は働きたい人が溢れていました。
多少理不尽な職場環境でも
「それでも働きたいんです」
といった時代だったため、困ったことに
「何か問題が起きても、部下のせいにしたらいいんだ」
「だって、働きたい人なんてわんさかいるんだし」
と考えていた上司もいたからでしょう。
そんな悪い考え方が、あまりにも多くの企業にあったため、日本社会にがっちり定着してしまい、それがさも当たり前となってしまっていたからです。
その異常な考え方はやがて、指導される側の人達の心理にも作用しはじめ
「どの会社もそうなっている」
「会社ってそういうところなんだな」
と受け入れられてしまったからではないか?と見ています。
「そんな悪しき風習はうちには関係ない」
「我が社は誠実でありたいんだ!」
もし社長がそうお考えなのであれば、私は社内のマネジメント面にも
わかったフリをされた方が反省する形にする
を取り入れる事をおすすめします。
変えること自体は困難です。
しかし、実は方法さえあっていれば効果はすぐに現れるものです。
社内が完全に変わりますと
「あれ? そういえばなんで私達は平気で部下のせいにしてしまっていたんだろうか?」
「我々はとんでもないことを平気でしてたんだ・・・」
となり、
「え〜・・・昔ってそんな状態だったんですか」
「信じられない」
などと、変わってから入ってきた社員やスタッフ達後輩からは、まるで他社の話のように驚かれるようになるくらいです。
なぜすぐ効果が現れるのか?
それはきっと、店舗型のビジネスで働く人達は
「売れなかったら売る方に問題があったからだ」
といった考え方を根本に持っている人達だからだと見ています。
「売れないのは売り手に問題があるからだ」
この考え方は、その人をとても強くしてくれる宝です。
その宝をどうしたらうまく活用でき、会社を変えられるのか?
それは、社長の決意と行動で決まるのです。