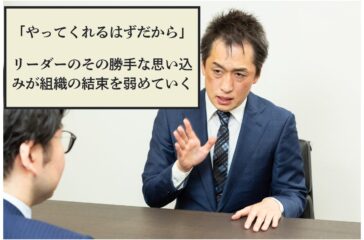
第487号 人の気持がよくわかっているリーダーなのに、結果を出せなかった理由
「このままではダメなんです」 数十年間、自ら現場の先頭に立ってきた社長がおっしゃいました。 社長は数日前まで入院されていました。 仕事中に倒れてしまったのです。 社長ありきの仕事ばかりだった現場は大混乱。 従業員はもちろん、多くのお客様に迷惑をかけてしまったとの...
 専門コラム今週のマネジメント 伊東 翼 執筆のチェーン経営に役立つコラム
専門コラム今週のマネジメント 伊東 翼 執筆のチェーン経営に役立つコラム 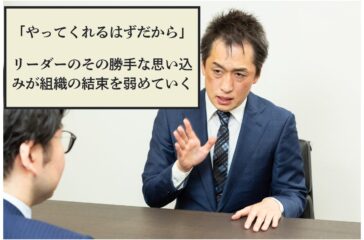
「このままではダメなんです」 数十年間、自ら現場の先頭に立ってきた社長がおっしゃいました。 社長は数日前まで入院されていました。 仕事中に倒れてしまったのです。 社長ありきの仕事ばかりだった現場は大混乱。 従業員はもちろん、多くのお客様に迷惑をかけてしまったとの...
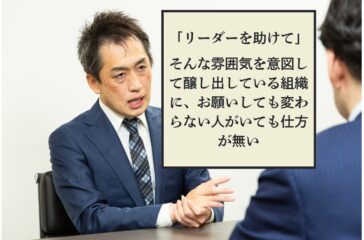
「頼むからちゃんとやってくれ」 「何度言ってもダメでした」 「何かいい方法は無いでしょうか」 ある社長がおっしゃいました。 お願いしたはずなのに、しばらくするとまた同じような失敗を繰り返される。 店舗型のビジネスにおいて、そんな体験をされているリーダーもいらっし...
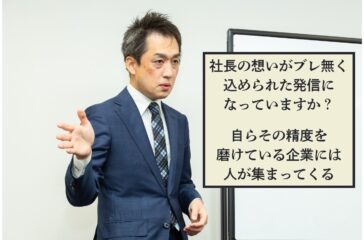
「『電話のコード抜いておけ』なんて言ってましたから」 ある社長がおっしゃいました。 バブルの頃は従業員応募の電話が鳴り止まなかったため、こう指示したことがあったそうです。 当時は電話応対の良し悪しだけで大半をお断り。 会社が欲している人材だけを厳選して採用することが...
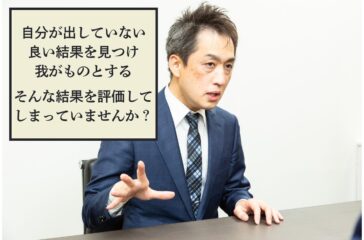
「ズルしていた社員はいなくなりました」 「ズルを容認してた社員も」 ある社長がおっしゃいました。 店舗型のビジネスにおいて、このワードを使っている社長もいらっしゃるのではないでしょうか? 「結果を出しなさい」 実はこのワードには毒が含まれています。 ...
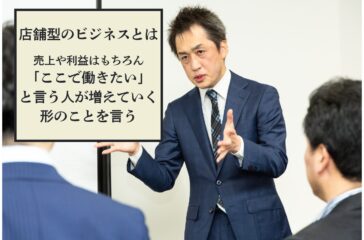
「ここに新店を出そうと思ってまして」 ある社長からのご相談でした。 私の返答は A社には「よしたほうがいいのでは?」 一方、B社には「いいと思います」 そう判断した理由は立地条件や会社の収支を見せてもらい、それが悪かったから、良かったからではありません。 そ...
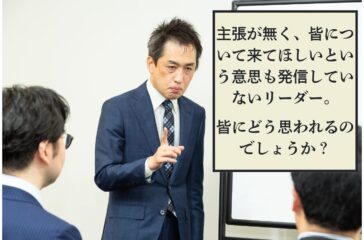
「頑張らないけど在籍していたい人なんて、そもそも来ないですから」 ある社長がおっしゃいました。 まるで「運が良いからうまくいってます」というニュアンスですが、正確に表現しますと「『頑張らないけど在籍はしていたい』という人は、そもそもいなくなるし、来なくなるようにでき...
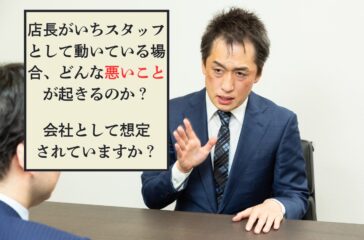
「伊東さん、やっぱり店長はいちスタッフとして動いてはいけないんでしょうか?」 ある社長から質問でした。 社長としては、店長は店舗の監督。 いちスタッフとして動くのではなく、これからは店舗全体を見る目を持ち、自ら判断して数字を上げていく監督者であってほしいという方針に...